広報ひだか平成28年8月号 防災特集
もしもの地震への備えをいつもお願いします!
9月1日は、「防災の日」です。大正12年9月1日に発生した「関東大震災」にちなんで、国民の地震等の災害についての認識を深めることを目的に、昭和35年に制定されました。日高市においては、今後30年以内に発生する確率が高いとされる地震において、最大深度は市の中央から東側の区域で6弱、西側の区域では5強と想定されています(平成25年埼玉県地震被害想定調査から)。
地震は、突然やってきます。そんなもしもに備えて、いつも心がけたいことをまとめました。これを機会に、日頃からできる家庭の防災対策に取り組んでみましょう。



画像は市の主な備蓄品
1 日頃からの心がけ
非常時の連絡方法を家族と相談
非常時に連絡方法や集合場所・避難場所は相談していますか。もし、災害が日中に起こったら…学校、仕事、外出等、家にいるとは限りません。非常時の連絡方法は、あらかじめ複数相談しておきましょう。

災害伝言ダイヤル「171」
毎月1日と15日等に体験利用ができます。使い方をあらかじめ確認しておきましょう。
- 「171」をダイヤル…録音は「1」再生は「2」
- 登録可能番号…すべての電話番号
- 録音時間…1件につき30秒
埼玉西部消防局のメール配信サービス
日高市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市の火災情報や気象情報、地震情報などを携帯電話にメールで配信します。
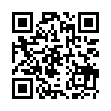
避難場所と避難経路の確認を
自宅や学校・勤務先から避難場所への避難経路も確認しておきましょう。平常時には実際に歩いて安全に通行できるか確認しておきましょう。
2 食糧・飲料水等の備蓄
交通インフラの遮断により、支援物資がすぐに手に入るとは限りません。
例えば、日頃から利用している食料品や生活必需品を少し多めに買い置きし、定期的に古いものから消費していく「日常備蓄」なら少しの工夫で災害に備えることができます。
これだけは備えておこう!必要最低限の備蓄品リスト

備蓄品は持ち出しやすい玄関や車庫等に保管しましょう。
- 非常食(レトルト・缶詰等)…最低3日分
- 飲料水(1人1日3リットルが目安)…最低3日分
- 貴重品
- 懐中電灯
- 軍手
- 着替え
- 筆記用具
- タオル
- レインコート
- 救急袋
- 医療・衛生用品
- 予備電池
- はさみ・カッター
- ビニール袋
- レジャーシート
- 笛
- ラジオ
- 毛布
3 家の中・周りの安全点検
平成28年4月に発生した熊本地震では、古い耐震基準で建築されていた昭和56年以前の建物が主に被害を受けました。また、1回目の地震では被害がなくても、2回目の地震により、被害が出たケースもありました。
大地震時に自分や家族を守るためには、地震に対して自分の家が安全かどうか診断し、診断結果によっては耐震改修をする必要があります。特に自宅に被害がなければ、避難する必要はありません。そうしたことからも耐震診断を受けましょう。地震保険についてもご検討ください。
家の中の安全点検
- 避難の妨げにならないように家具を配置しているか
- 寝室には、倒れやすい大きな家具が置いてないか…大きな家具のない部屋を寝室にしましょう。若しくは、L型金具やツッパリ棒などの転倒防止器具により家具を固定しましょう。
- 窓ガラスは飛散しにくいものか…強化ガラスに替えたり、紫外線防止のフィルムを貼ることにより、飛散防止ができます。また、ガラスの破片によるケガを防止するため、スリッパなどを身近に用意しておくのもよいでしょう。
- 頭の上から落下するものはないか…背の高いタンスや冷蔵庫の上に物などは置かないようにしましょう。また、吊り下げ式の蛍光灯などは、補助金具を取り付けましょう。
家の周りの安全点検
- 屋根や壁などに破損やひび割れなどがないか…不具合箇所があったら、早めに修繕しましょう。
- 家の出入口は、自転車・ベビーカーなどは置いてないか通路や出入口には、避難のじゃまになるような物は置かないようにしましょう。
- テレビのアンテナやガスボンベなどはしっかり固定されているか…地震などの揺れにより、落下や転倒のおそれがあるので、しっかり固定しましょう。
耐震診断
市では、昭和56年以前に建築された木造住宅に対して、簡易的な耐震診断を無料で行っています。また、木造住宅の耐震診断、耐震改修を行うかたに、診断費用、改修費用の一部を補助しています。詳しくは、都市計画課へご相談ください。
日頃から防災対策を

防災専門員 今野利弘さん
私は、市の防災専門員として、区・自治会などで組織する自主防災組織が行う防災訓練の指導などをしています。
大規模な災害のときは、市や消防機関が全ての災害現場の対応をすることは困難であると予想されます。そうしたことから日頃から個人や家庭でできる「備え」と、地域の住民同士が協力し、組織的に活動する自主防災組織が重要となってきます。実際に阪神・淡路大震災では、家具や家屋の下敷きになり、救出された人の約8割が近所のかたに助けられました。
いつもの生活の中で、隣近所であいさつを交わすことで、もしもの災害のときに「助け合うこと」「声をかけあうこと」「隣に住む人がどんな人で、どんな事情を抱えているかを知っていること」、そうしたことが、知識や家庭での備蓄よりも大きな防災につながります。
この機会に、いつもの生活をもう一度見直してください。
自主防災組織への参加
大きな災害が発生したとき、交通網の寸断、同時に発生する火災などにより、市・警察署・消防署などの公共機関が体制を整えるまでに時間を要します。阪神・淡路大震災では、地震によって倒壊した建物から救出され生き延びることができた人の約8割が、家族や近所の住民等などの「自助」「共助」によって救出されており、消防、警察及び自衛隊などの「公助」によって救出された人は約2割であるという調査結果があります。
そんなときに力を発揮するのが、「地域ぐるみの防災活動」自主防災組織です。いざというときに備えて、自治会活動の一環として自主防災組織へ参加しましょう。
避難行動要支援者への協力
高齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児・傷病者・日本語が不自由な外国人のかたたちは、災害時の避難行動や言葉の理解などで大きなハンデを負うことになります。日頃からコミュニケーションをとりあって、災害時には相手に適した誘導方法で早めの避難ができるように協力しましょう。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年12月19日

















