高麗郡建郡1300年の歴史と文化
歴史
日高市では、「高麗(こま)」という地名や、「高麗神社」や「高麗川」などの名称を目にします。
これは、古代朝鮮半島「高句麗(こうくり)」と深い関わりがあったことを表しています。
716年(霊亀2年)に、「高麗郡」が置かれ、高麗人たちが移住しました。
「郡」とはいくつかの町村をまとめた広い行政区画のことです。
江戸時代の末頃には、日高市・飯能市・鶴ヶ島市の全域と、狭山市・川越市・入間市・毛呂山町の一部を含んだ範囲を「高麗郡」と呼んでいました。
ふるさと『日高市』の歴史を知ろう!

今から、およそ1300年前、現在の日高市を中心に「高麗郡」ができました。
どのようにして「高麗郡」ができたの?
高麗郡は「高句麗」という国から日本に渡って来た人たち(「高麗人」と呼ばれる渡来人)によってつくられました。
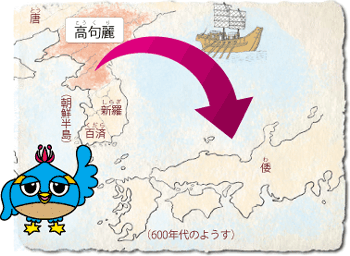
高句麗は、中国の東北部から朝鮮半島にかけて約700年間(紀元前37年頃から668年(天智7年))栄えた大きな国でした。
その高句麗は、唐(今の中国)や新羅と戦っていましたが、戦いにやぶれ、668年(天智7年)にほろんでしまいました。
国がなくなってしまったため、高句麗から海を渡って日本に来る人たちが多くいました。その人たちを日本では「高麗人」と呼びました。
- 高句麗・新羅・百済などから来た人たちを「渡来人」と言います。
- その当時、日本は倭(わ)とよばれていました。

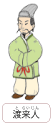
716年(霊亀2年)(今から1300年前)に、関東各地(当時の7カ国)に住んでいた「高麗人」1,799人が武蔵国に集められ、「高麗郡」ができました。
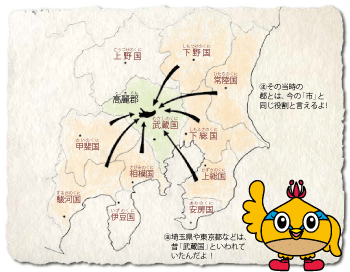
「高麗郡」ができたことは、昔の歴史書である『続日本紀(しょくにほんき)』に書かれています。
高麗人たちの渡来人は、大陸の進んだ技術や文化を伝えました。
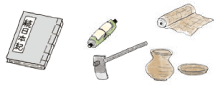
その時、どんな人が中心になっていたの?
高麗郡をつくった時のリーダーが「高麗王若光(こまのこきしじゃっこう)」という人で、日高市にはゆかりの建物があります。
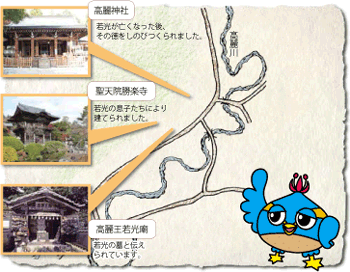
若光は、666年(天智5年)高句麗よりのつかい(戦いの援軍をお願いするため)として、日本へやってきました。
しかし、668年(天智7年)高句麗がほろび、帰れなくなってしまいました。
703年(大宝3年)、日本の朝廷より「高麗王」の姓を与えらえました。その時から「高麗王若光」と名のることになりました。
歳をとって、白ひげをはやしていたので「白ひげ様」ともいわれたとの伝説も残っています。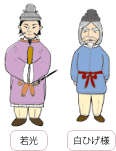
約1200年間続いた高麗郡は、1896年(明治29年)入間郡に組み入れられて、その名が消えました。

その時の高麗郡の範囲は、日高市と鶴ヶ島市の全域、それに飯能市や川越市、狭山市、入間市の一部まで入っていました。
なぜ、「高麗郡」があったことがわかるの?
日高市内から、「高麗郡」がつくられた時の品々が多く発見されています。
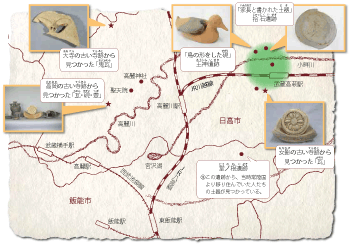
市内には、高麗郡がつくられた時に建てられた古い寺跡が3か所あります。
そこからはお寺の屋根につかわれた瓦が多く発見されています。
また、当時の役人が使っていたさまざまな品物が武蔵高萩駅周辺から見つかっています。
参考
高麗郡1300年小学生版リーフレット (PDFファイル: 2.0MB)
高麗郡の文化
太古から近世まで、人々の営みが脈々と息づいてきた日高。
その歴史の足跡をしのび、のんびりと一日探訪してみませんか。


高麗王若光の徳をしのび、その霊を祭って建立されたもので、出世開運の神さまとして信仰されています
高麗家住宅


高麗神社の裏手にあり代々宮司を務めた高麗家の住宅。かやぶきの入母屋造りの住宅として県下で最も古いものとされており、国指定重要文化財に指定されています。
高麗郷古民家(旧新井家住宅)


敷地内には、江戸時代末から明治時代前半に建てられた母屋と客殿を中心に納屋と2棟の土蔵があり、通りに面した箇所には人目を引く石垣や白壁が築かれ、高麗郷の美しい景観を創り出しています。
高麗石器時代住居跡


約4500年前の縄文時代中期のもの。円形で直径6メートル。多数の出土、装飾品、石皿などが出土。柱を立てた穴もあります。
聖天院


高麗山聖天院勝楽寺と号し、山門の独特の美しさと厳かな雰囲気に胸が打たれます。春の桜の季節は池に桜が美しく映えて見事です。
日光街道


江戸時代、八王子にいた千人同心が日光東照宮の火の番を勤めるために往来した道。現在は国道407号で当時の面影を今に伝えています。
台滝不動尊


江戸時代末期に台山大沢堀を作り、円福寺庭の不動様を移して祀り、1900年(明治33年)に現所在地に移設。年間を通じて、参拝客が絶えません。
台の高札場跡(江戸時代の掲示板)

高札場とは高札を掲げる場所で、村の中央、代官・名主の屋敷前などに設けられて、重要な事項、幕府の基本姿勢の周知徹底を図ることを目的としたものです。
野々宮神社


この地方では高麗神社より古いと言われている神社で、境内には土俵があり、秋には「おらがむらの相撲大会」が開催されます。
霞野神社


1910年(明治43年)に中沢、女影地区の12社を合祀してできました。本殿は江戸時代末期の作と考えられています。境内には、1335年(建武2年)に足利尊氏の弟直義と鎌倉執権北条高時の遺子相模二郎時行が女影の地で戦った中先代の乱の古戦場の碑と説明があります。
このほかにも、日高市にはたくさんの文化財があります。
詳細は歴史・文化財のページをご覧ください。
早わかり高麗郡入門Q&A
高麗郡とは何かという基本的なことが誰にでも分かるようQ&A形式でまとめられた高麗郡ガイドブックです。

- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2017年05月12日

















