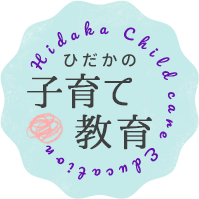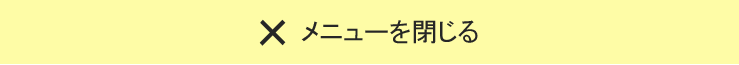出産育児一時金
日高市国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により支給されます。
- 出産した日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できません。
- 健康保険に加入していた人が、退職後6か月以内に出産したときは、原則、加入していた健康保険へ申請となります。
給付の内容
50万円
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、妊娠12週(85日)以降の死産および流産の場合は、48万8,000円になります。
- 双生児以上の分娩に対しては、出生児数に応じて支給します。
(注釈)産科医療補償制度とは、妊娠・分娩に際して重度脳性マヒとなった出生児およびその家族の経済的負担を補償する制度です。
支給方法
直接支払い制度
市から医療機関等へ直接出産費用を支払います。保険年金課での手続きは必要ありませんが、事前に出産予定の医療機関等と直接支払い制度に関する委任の契約が必要です。
- 出産費用が給付額を超える場合は、医療機関などに差額分をお支払いください。
- 出産費用が給付額を下回る場合には、その差額分の支給を市に申請することができます。
本人へ支給
直接支払い制度を利用しない場合や、差額分の請求をする場合は、下記の申請に必要なものを持参し、市役所1階3番窓口へお越しください。
申請に必要なもの
- 分娩医療機関発行の領収証および明細書
- 直接支払い制度の利用の有無が確認できる合意文書
- 出産した人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 振り込み口座(世帯主名義)がわかるもの (注釈)公金受け取り口座を利用するときは不要
- 窓口に来られる人の顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
受取代理制度
直接支払い制度の準備が整っていない医療機関での申請の場合、医療機関によっては出産育児一時金受取代理制度を利用できる場合があります。直接支払い制度と同じく世帯主に代わり医療機関が出産育児一時金の受け取りを行う制度ですが、申請方法が異なります。詳しくは、担当までご連絡ください。
海外で出産したとき
日高市国民健康保険に加入中に海外で出産した場合は、世帯主からの申請により、48万8千円(令和5年3月31日以前に生まれた場合は、40万8千円)が支給されます。
申請に必要なもの
- 出生証明書
- 出生証明書の日本語訳(翻訳者の氏名・住所が記載されたもの)
- 分娩医療機関発行の領収証および明細書
- 調査に関わる同意書 調査に関わる同意書(海外出産用)(PDFファイル:128.9KB)
- 出産した人のパスポート(渡航記録や期間の確認ができるもの)
- 妊娠届や母子健康手帳など、妊娠の事実確認ができるもの
- 出産した人と世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 振り込み口座(世帯主名義)がわかるもの (注釈)公金受け取り口座を利用するときは不要
- 窓口に来られる人の顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
支給の厳格化について
海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しています。国内に住民票を有しているものの、実際には海外に長期間滞在する人が、海外出産に係る出産育児一時金の支給申請を行った場合には、その人が日高市に生活の本拠を有し、かつ、国民健康保険の被保険者資格を有する人であるかについて住民基本台帳担当部門と連携し厳格に審査を行います。また、不正請求の疑いのある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。
出産費資金貸付制度
直接支払い制度・受取代理制度を利用できない医療機関で出産を予定している場合、出産に必要な資金を出産育児一時金が交付されるまでの間、一時的に借り入れることができます。
貸付金額
出産育児一時金の80パーセント以内
返済方法
出産後に支給される出産育児一時金を返済に充てます。
(注釈)出産育児一時金の支給時に貸付人にお渡しする金額は、貸付額を差し引いた残りの額です。
手続きできる人
次のいずれかに該当する国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主
- 出産予定日まで1か月以内の人(1号申請者)
- 妊娠4か月以上で、医療機関などに一時的な支払いが必要となった人(2号申請者)
申請に必要なもの
- 顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 母子健康手帳
- 振込口座(世帯主名義の口座)がわかるもの
- 医療機関の請求書または領収書(2号申請者のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年10月31日