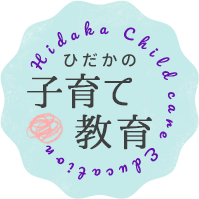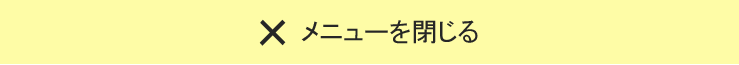児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚、死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている人や、子どもを育てている父または母に一定の障がいのあるときに支給される手当です。手当は、申請を受け付けた翌月分からとなります。
子どもとは、18歳になった年の年度末(3月31日)までの子です。一定の障がいのある子どもの場合は20歳になるまでです。
対象となる人(支給要件)
次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
(注釈)平成22年8月分から、父子家庭の人にも支給されています。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がいがある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
(注釈)
- 婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情がある場合(内縁関係など)を含みます。
- 離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合でも、「父または母による現実の扶養を期待することができないと判断される場合」は、遺棄に該当するなど、事実関係を総合的に判断します。
- 父、母、養育者または児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合は差額分の手当を受給することができます。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。
手当が受けられない場合
- 申請する人や子どもが日本国内に住所を有しないとき
- 子どもが児童福祉施設など(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 子どもが父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障がいの状態にあるものを除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
手当額と支給月
支給月は、5月(3月、4月分)、7月(5月、6月分)、9月(7月、8月分)、11月(9月、10月分)、1月(11月、12月分)、3月(1月、2月分)の6回となります。
手当額は、物価の変動に応じて改定されています。
令和7年4月分から月額が次のとおり改訂されました。
| 子どもの人数 | 全部支給 | 一部支給 (所得に応じて決定されます) |
|---|---|---|
| 1人の場合 | 4万6,690円 | 4万6,680円から1万1,010円まで |
| 2人目以降加算額 | 1万1,030円 | 1万1,020円から5,520円まで |
所得制限
資格のある人は、所得に関わらず申請できます。ただし、申請する人やその配偶者、および同居など生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
| 扶養人数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 配偶者・扶養義務者 孤児などの養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
| 5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
| 6人 | 297万円 | 436万円 | 464万円 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額。
- 本人の場合は、(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき10万円、(2)特定扶養親族一人につき15万円
- 孤児などの養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族一人につき6万円
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除など)+養育費の8割相当額-8万円-下記の諸控除
| 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 寡婦(夫)控除 (受給者が父または母の場合は控除しない) |
27万円 |
| 特別寡婦(夫)控除 (受給者が父または母の場合は控除しない) |
35万円 |
| 障がい者控除 | 27万円 |
| 特別障がい者控除 | 40万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
| 配偶者特別控除 | 当該控除額 |
申請手続き
必要書類をお持ちのうえ、子育て応援課にて認定請求の手続きをしてください。 申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
認定請求に必要な書類
- 請求者(保護者)と子どもの戸籍謄本(注釈1)
- 申請者(保護者)名義の銀行等の口座番号などが分かるもの
- 申請者(保護者)の基礎年金番号を確認できるもの
- 申請者(保護者)と子どもが加入する医療保険の保険者から交付された「健康保険証」、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等(ひとり親家庭等医療費の申請に必要となります)
- 申請者(保護者)と子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等)(注釈2)
- 申請者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注釈1)離婚直後は新しい戸籍謄本がすぐにはできないため「離婚届受理証明書」でも受け付けできます。後日戸籍ができ次第速やかに提出してください。
(注釈2)マイナンバーを使用して、市区町村間の情報連携により所得の確認を行います。所得等の申告が済んでいない人は、申告する必要があります。
- 申請に必要な書類は、必ず事前にお問い合わせください。
- 申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。
その他
- 受給資格者になった人は、届け出の内容が変わったときには、変更や資格喪失などの手続きが必要です。また、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- JR通勤定期乗車券の割引制度があります。
児童扶養手当の一部支給停止
児童扶養手当法第13条の3の規定により、児童扶養手当の受給から5年を経過するなどの要件に該当する受給者は、手当が一部支給停止(2分の1の減額)される場合があります。
一部支給停止が適用されない人
下記に該当する人は、必要な手続きを行えば、一部支給停止はされません。
- 仕事(就業)をしている
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- 障がい、負傷、疾病、要介護状態などにあるあなたの親族をあなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
上記に該当しない人は、子育て応援課までご相談ください。
一部支給停止が適用とならないために必要な手続き
対象となる人には、個別にお知らせを送付しています。
定められた期間内に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を子育て応援課まで、提出していただきます。
初回の手続き後においても、毎年8月に行う現況届提出時に同様の手続きが必要です。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年12月23日